今年は4会場での開催となった夏の始まりを告げる「夏びらき MUSIC FESTIVAL」(以下、夏びらきフェス)。一夏に複数の会場でフェスを開催する珍しい形態のフェスを主催するのは、kawara CAFE&DININGなどを手がける「株式会社エスエルディー」のプロデューサー、高橋マシ氏。上京してからフェスを立ち上げるまでの波乱万丈なエピソードから飲食店を手がける会社がフェスを主催する理由、そしてフェスを作っていく上で大切にしていることを聞きました。
夏びらきフェス主催 高橋マシ氏インタビュー
-まずは自己紹介をお願いします。
「株式会社エスエルディー」という会社でプロデューサーをやっています高橋マシです。「kawaraCAFE&DINING」などの飲食店、ライブハウス「代官山LOOP」を、全国各地で複数経営している会社で、僕はイベント事業を主に担当しており、今では毎年日本各地で「夏びらきフェス」を開催しています。
-「夏びらきフェス」はどういった経緯では始まったんですか?
まず会社の説明をすると、創業したのは15年前くらいで、イベントオーガナイザーやDJをやっている5人が集まってクラブイベントの制作事業から始まった会社なんです。僕が18歳で上京して、23歳のときにスタートしました。それまで僕自身もDJをやったり、自身のイベントをオーガナイズしたり、パーカッションの演奏もしてました。SOIL & “PIMP” SESSIONSやRickie-Gは、初期のころから友達で、そういったバンド界隈の繋がりもあったこともあり、青山LOOPっていうクラブの昼の時間帯でライブハウスをやらせてもらったりもしました。そこから「自分たちのカフェが欲しいよね」って言う話が出て、渋谷・神南にkawara CAFE&DININGを作ったことをきっかけに飲食事業が始まって今に至ります。
-その延長線上にあるのが「夏びらきフェス」という位置づけですか?
「夏びらきフェス」はそれまでの「自分たちのカフェを作りたい」、「自分たちのライブハウスを作りたい」の流れと同じ「自分たちのフェスを作りたい」といった思いからスタートしたイベントですね。
-23歳で会社を立ち上げてイベント制作事業を始めるまでも個人でイベントを打っていたりしたのですか?
ちょっと話が長くなるんですが、順を追って説明すると、若いときは地元では、いわゆるヤンキーと言われる存在だったんですよ(笑)。中学生のときからやんちゃな仲間たちとつるんでいて。音楽もそうですが、ファッションとか、喧嘩とか、何でもまっすぐに行動に移してやってましたね。初めてDJイベントを開催したのも高校生1年生のときでした。
-早いですね。
15歳のときに、一度親を泣かせてしまうような事件を起こしてしまったことがあって、このまま仲間とつるんで遊んでいるだけではマズイと思ってから、アルバイトに打ち込み始めたんです。古着屋や居酒屋やBARで働いていたんですが、そのときの先輩たちに教えてもらった隣町のクラブに、東京から沢山のDJや、外タレのDJがプレイしに来る素晴らしい場所がありまして。その当時からDJのNORIさん、須永辰緒さん、Basement Jaxx、JOAQUIN “JOE”CLAUSSELLなど沢山のDJプレイを見に通い詰めましたね。
DJだけではなく、他にも色んなアーティストのライブを観て、Monday満ちるさんのライブを観にいったときに、ドラマーだった江川ゲンタさんの演奏と人柄に完全に惚れ込んでしまって。それでゲンタさんが東京のTHE ROOMや西麻布YELLOWでレギュラーパーティをやってると知って、東京に会いに行きたいと思ったんですよね。
-とても羨ましい体験ですね。その後上京されたんですか?
ちょうど高校3年だったこともあり、卒業後の進路として東京の専門学校で音響や音楽の作り方を学びたいと思って、親にお願いしたら、今までしでかしてきた悪事のせいでお金はないと言われてしまって(笑)。それで学校の先生に相談したら、新聞奨学生の存在を教えてくれたんですよ。辛いだろうけど根性と体力だけは自信があったし、それでしか東京の学校に行く方法がなかったので、その制度を使って18歳のときに上京しました。
-新聞奨学生ってどんなことをするんですか?
当時は、一部学費を援助してくれるライトなコースと、学費全額負担するけど朝刊・夕刊・集金・勧誘など全部をやるハードなコースの2種類があって、もちろん自分は全額負担の方でした。配達は深夜の2時半から朝まで、その後9時から学校へ行き、また17時から23時まで新聞屋で働くような生活で、休みもほとんどないような生活でした。
-相当辛いですね。
もちろん覚悟もあったので、そういう意味では頑張れたんですが、やっぱり周囲も自分も18歳なんて遊びたい盛りじゃないですか(笑)。周りと自分を比べると惨めさを感じてましたね。その惨めさを痛感して過ごしている中で、ある土砂降りの雨の日の配達のときに、新聞を積んで停めていた自転車を酔っぱらいに倒されて、新聞がぐちょぐちょになってしまったことがあって、そのときにそれまで溜まっていた感情がバーっと溢れて、道端で大号泣してしまったんです。「俺は何をしてるんだろう」と。ワンワン道端で泣きまして(笑)。でも散々泣いた後に、ふと我にかえって、俺は新聞を配るために東京にでてきたわけじゃなくて、大好きな音楽で食っていくために東京に出てきたんじゃないかと思い出したんですよ。
-ドラマみたいな展開ですね。
本当にドラマみたいなこともたくさんありました。一緒に働いている同僚が次々とやめていく中、同じ寮にちょっと裏の世界の匂いがするヤバい人がいて、ちょっとした揉め事があって包丁を突きつけられたこともあったり。今では笑い話ですが、メディアに載せられるか分からない内容ですみません(笑)。ちなみにそのことは某テレビ番組で一部取り上げられました(笑)。
-載せられる範囲で載せます(笑)。
そんなこともありながらも、新聞配達はあくまで生活していくための手段だということに立ち返って、毎晩仕事が終わってから次の仕事が始まるまでの寝る時間を削って、渋谷のクラブに通い始めました。クラブのピークタイム前に新聞配達があるといって帰る若者がいる、しかも毎日来るっていうので先輩たちからとても面白がってもらって、そこで色んな人脈が一気に増えましたね。そこでできたご縁が広がって、会社の創業まで繋がってきた感じですね。
-かなりハードな生活だったと思いますが、仕事と学業の両立は大丈夫だったんですか?
そこはもう頑張りました。学校もちゃんと行って卒業もしましたし。でも本当に今思い返してもあれより辛いことなんてない!と言えるほどの生活でしたね(笑)。


















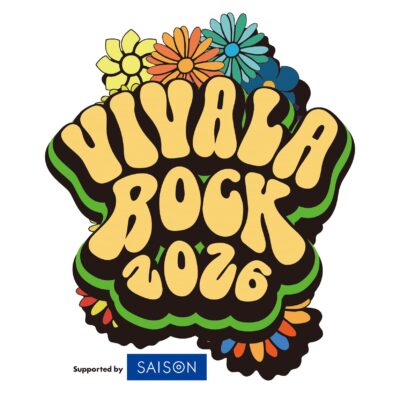


![【METROCK2026】メトロック、第4弾発表で[Alexandros]、T.M.Revolution、Da-iCEら18組追加](https://festival-life.com/wp-content/uploads/2026/02/a8347a5a9335fa241859ec05ad0dd30b-400x400.jpg)


